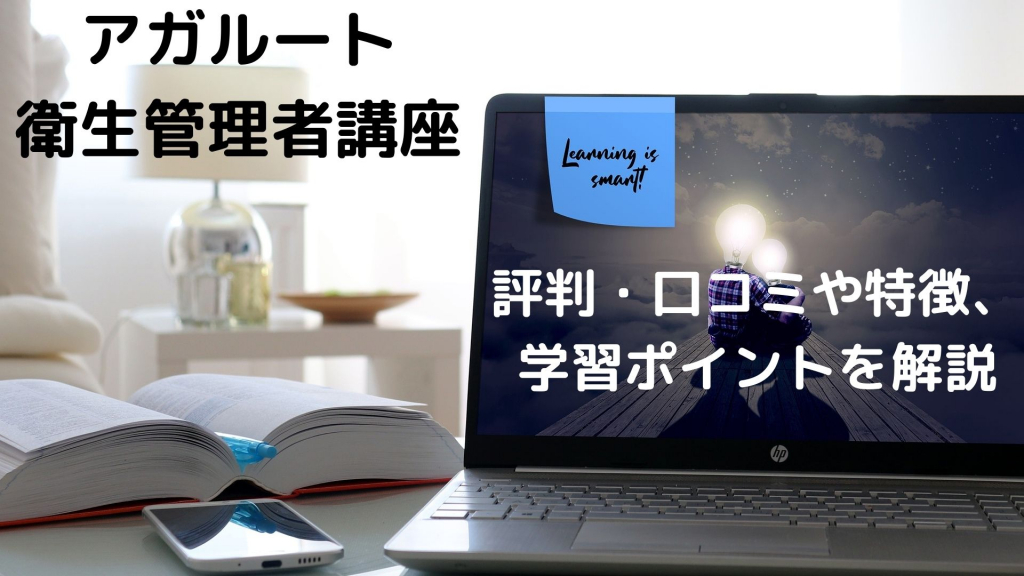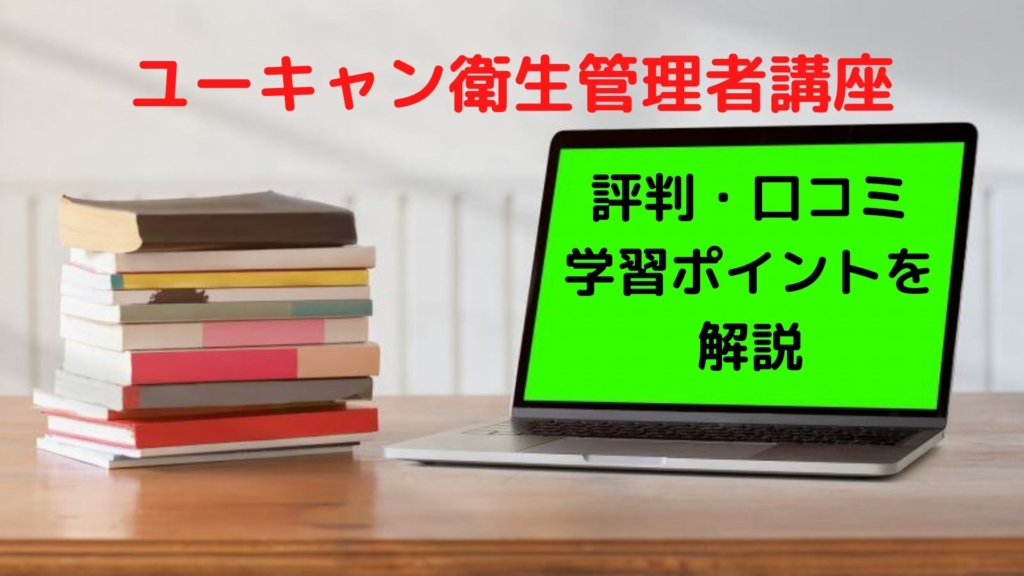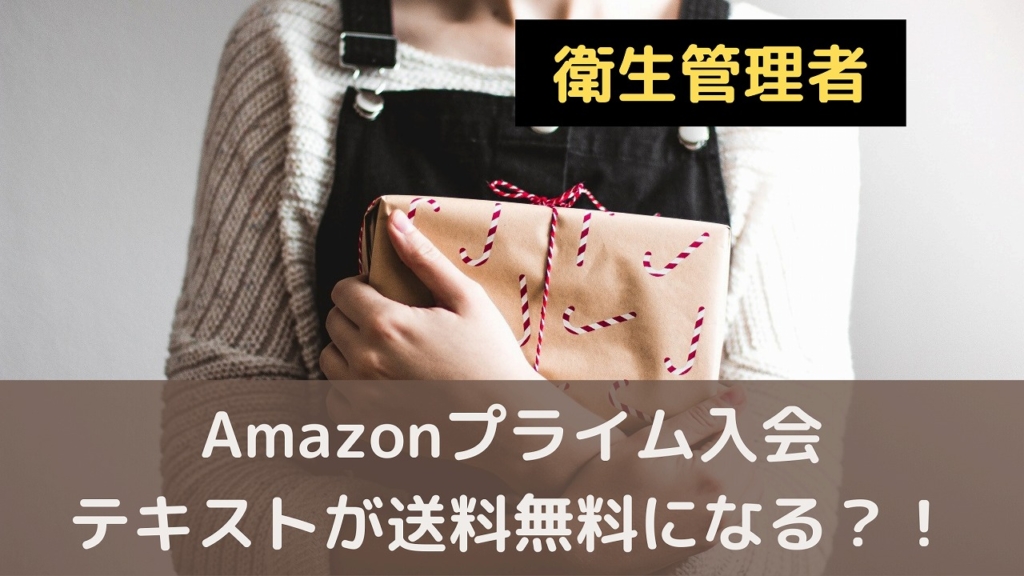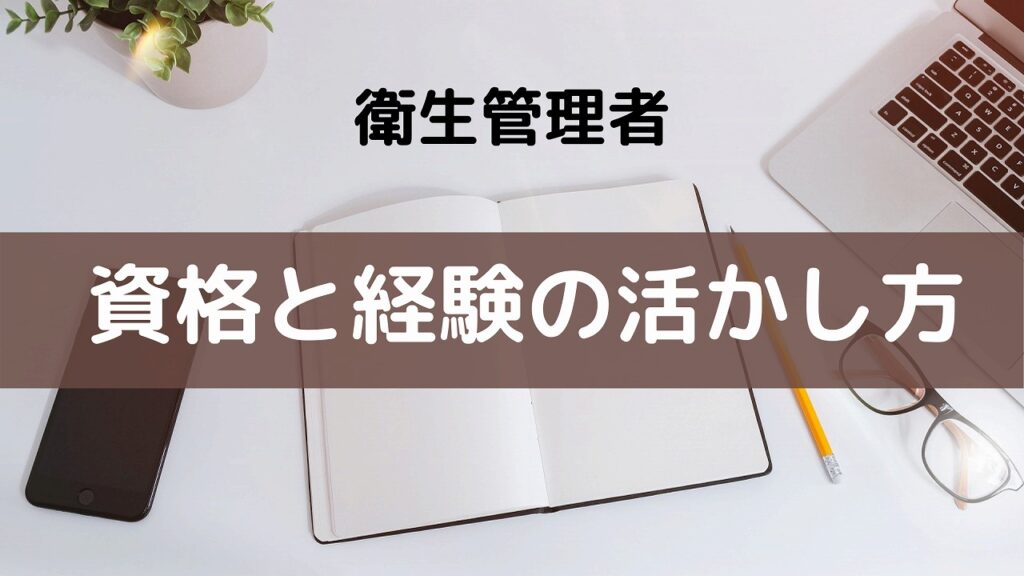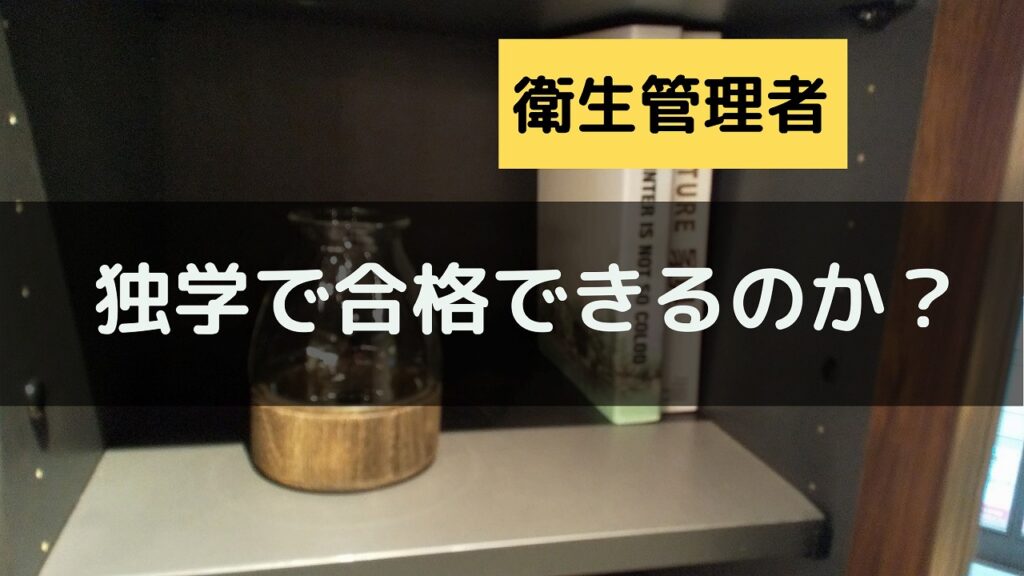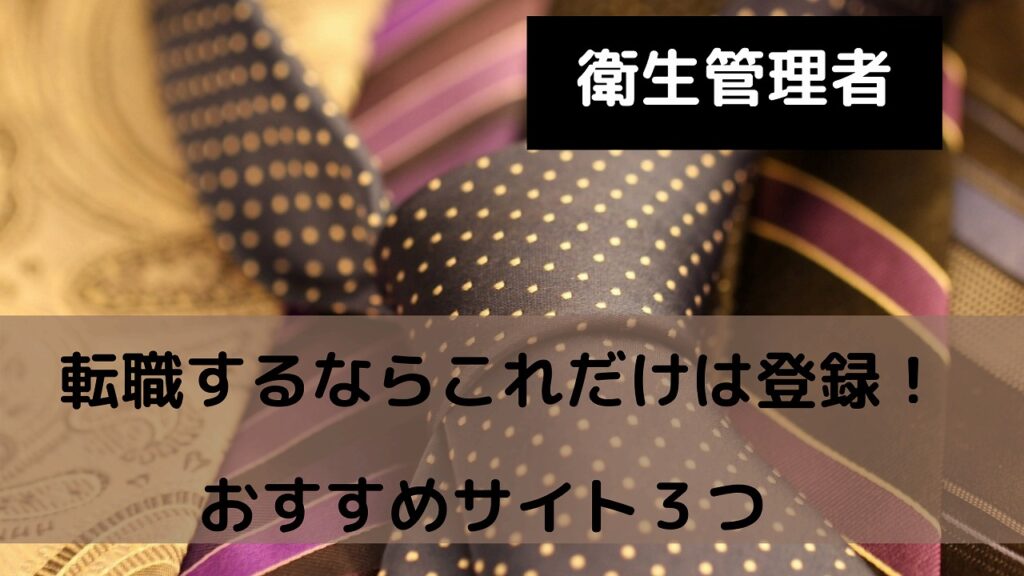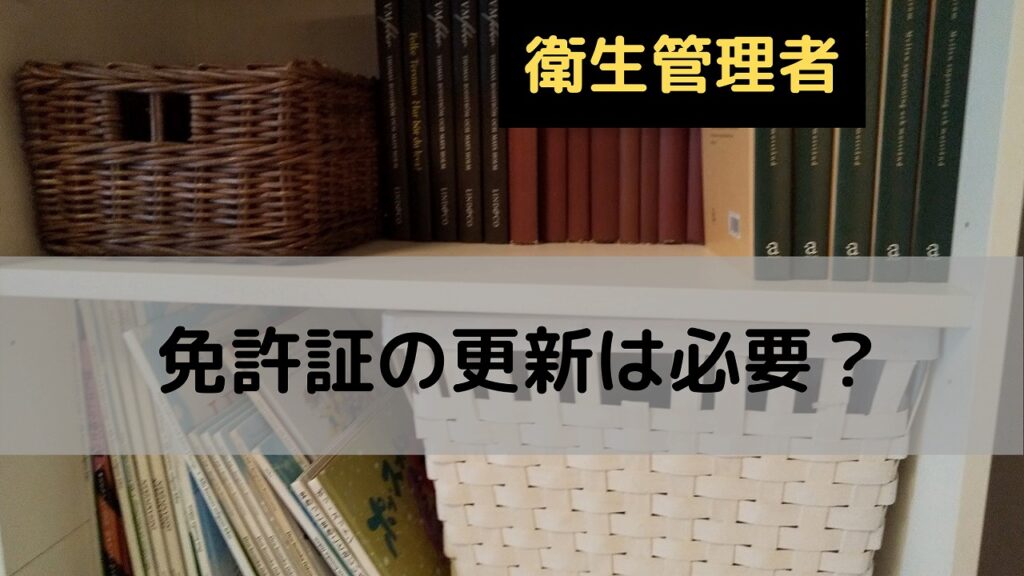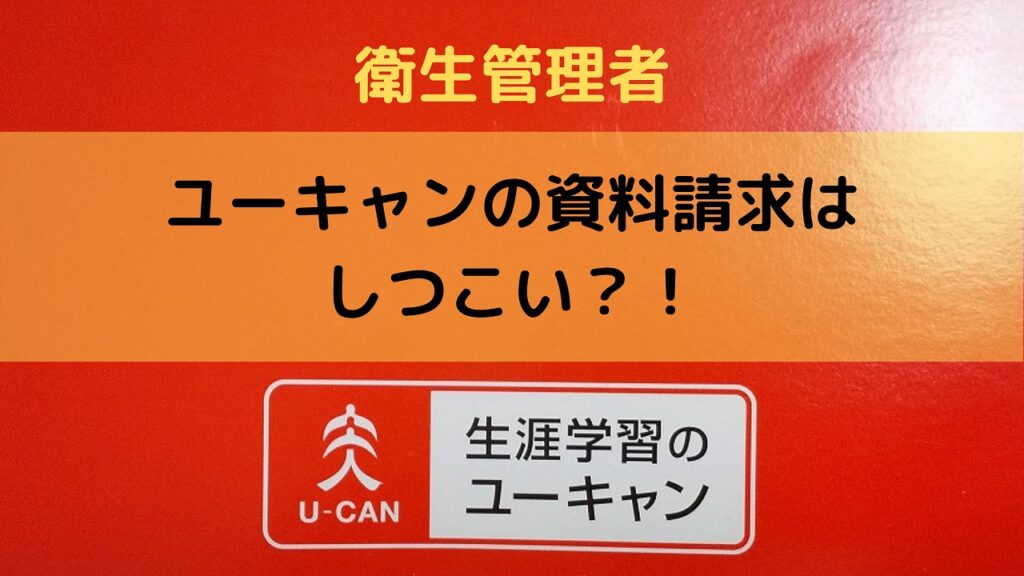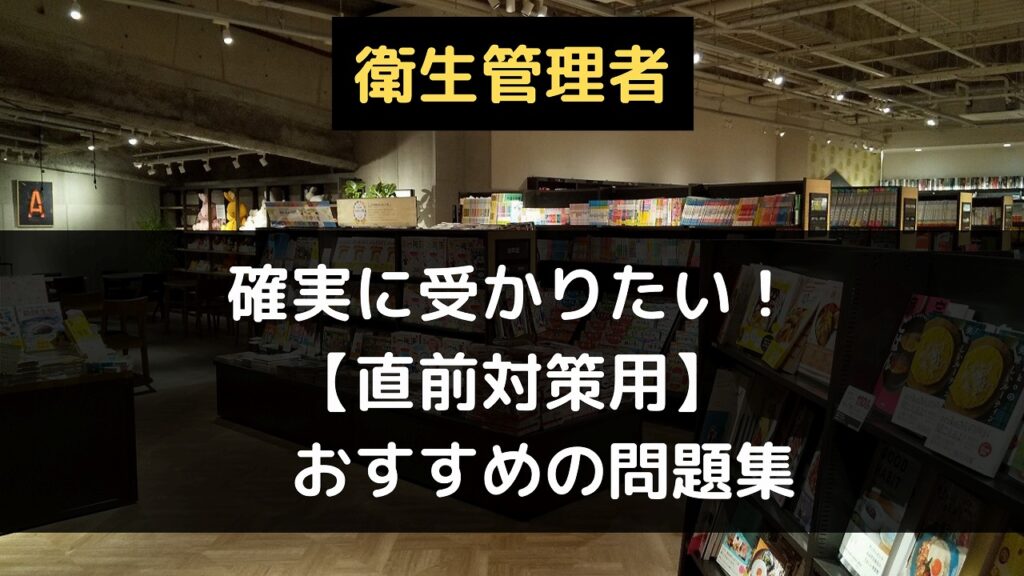衛生管理者– category –
-

【アガルート評判】衛生管理者講座の口コミや特徴、学習ポイントを解説
アガルートの評判が気になる衛生管理者講座の口コミ、特徴を教えて。 このような質問にお答えします。 記事でわかること アガルートの衛生管理者講座の評判、口コミアガルートの衛生管理者講座がおすすめな人アガルートの衛生管理者講座の特徴各教材につい... -

ユーキャン衛生管理者講座の評判・口コミや特徴、学習ポイントを解説
ユーキャンの衛生管理者講座の評判や特徴を教えて。 このような質問にお答えします。 記事でわかること ユーキャンの衛生管理者講座の評判、口コミユーキャンの衛生管理者講座がおすすめの人ユーキャンの衛生管理者講座の特徴ユーキャン衛生管理者講座のス... -

Amazonプライム入会で衛生管理者のテキストが送料無料になる?!
Amazonプライムに入会したら、送料無料になるの? こんな疑問にお答えします。 この記事でわかること Amazonプライムは通常配送無料有料オプションの配送も無料送料無料にならない場合その他の特典 こんにちは。 この記事を書いている かとひで... -

kindle版(電子書籍)で衛生管理者の資格勉強できるの?!
衛生管理者テキストってKindle (電子書籍)で読めるの? このような疑問にお答えします。 この記事でわかること 衛生管理者テキスト、過去問(kindle版 読み放題)衛生管理者テキスト、過去問(kindle版 読み放題ではない)衛生管理者の関連書籍、実... -

衛生管理者の資格と経験の活かし方とは?どんなメリットがあるのか?
衛生管理者の資格の活かし方を教えて 衛生管理者の資格取得のメリットは何?転職活動で衛生管理者の活かし方ってありますか? このような疑問にお答えします。 この記事でわかること どんな業種で重宝されているのか衛生管理者の業務は大きく分けて3つ... -

【2023年版】第一種衛生管理者を独学で合格する方法を解説
第一種衛生管理者試験って独学で合格できるの?独学での勉強方法ってあるの? 衛生管理者の独学は無理そうなので、通信教育とかはどうなのかな? 衛生管理者の独学って、どのテキストと過去問が良いのかしら? こんな疑問にお答えします。 この記事... -

【衛生管理者】転職するならこれだけは登録!おすすめのサイト3つ紹介
インターネットで衛生管理者の転職サイトの選び方ってあるの? 転職サイトの種類ってあるの? このような疑問にお答えします。 この記事でわかること 【衛生管理者】転職するなら、必ず登録しておくべきサイト3つ 【衛生管理者】転職サイトと転... -

衛生管理者の免許証は更新手続きが必要?法令が改正したらどうするの?
衛生管理者試験に合格したけど、免許証の更新ってあるの?法令改正の最新情報ってどこでわかるの? このような質問にお答えします。 この記事でわかること 衛生管理者の免許証には、有効期限があるか関連資格には、免許証の更新の必要なものはあるの... -

【ユーキャン無料資料請求】しつこいの?申し込み期限やいつ届くのか解説
ユーキャンの資料請求って無料なの?複数資料請求ってできるの?資料請求したら、いつ届くの? しつこい電話や、はがきはあるの?資料請求の方法ってどうするの? このような疑問にお答えいたします。 この記事を書いているひと かとひで 1975年生... -

第一種衛生管理者試験に確実に受かりたい!【直前対策用】おすすめの問題集
直前になって不安になってきた… 衛生管理者試験の直前にできる問題集ってあるの? こんな疑問にお答えいたします。 この記事でわかること 【衛生管理者試験】直前対策問題集はこんなひとにおすすめ 【衛生管理者試験】直前対策用 問題集2冊 こんに...