 疑問のある男性
疑問のある男性QC検定2級の【裏ワザ】ってあるの?
最短で合格するテクニックを教えて!
- よく出る公式だけ覚える
- 過去問の選択肢を暗記する学習法
- 選択肢から逆算する学習法
- 間違いノートを作らない
- 捨て問を決めて時間配分する
こんにちは。
この記事を書いている かとひで です。
私はこんなひと。


- 1975年生まれ、高卒
- QC検定2級を一発合格
- 品質部門に従事して15年
QC検定3級はスムーズに合格できたけれど、2級に挑もうとした瞬間、「なに?急に難しい…」と感じていませんか?
実はその感覚、まったく正しいんです。
2級は範囲が広く、専門用語も多く、計算問題も格段に複雑になるため、3級とは別物と考えるべきレベル。
でも、限られた時間の中でも効率よく合格を目指すことは、可能なんです。
そこで本記事では、効率よく合格を狙うための【裏ワザ】的なテクニックを厳選して5つ紹介します。
初受験の方はもちろん、一度つまずいた経験がある方にも役立つ内容です。
「効率的に学習したい!」「時間がないけど受かりたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
よく出る公式だけ覚える


「QC検定2級で、“よく出る公式だけ覚える”」という学習法は、まさに合格最短ルートの裏技的手法です。
なぜなら、範囲が広く、すべての公式を暗記しようとすると時間も労力もかかりすぎるため。
出題頻度の高い公式だけを狙い撃ちで覚えることで、効率よく得点源を確保できます。
🔶学習法の目的
- 満点を目指さず、合格点(70点)に集中する
- 出題傾向を分析して、「得点ゾーン」だけを重点学習
- 実践に強い、解ける力を優先
✅ ステップ1:頻出公式リストを作成する
▼主に出やすい公式(例)
| 分野 | 頻出公式 | 出題理由 |
|---|---|---|
| ヒストグラム・分布 | 範囲、階級値、度数、相対度数など | グラフ読解と絡めて出やすい |
| 管理図 | 管理限界(±3σ)や中心線の公式 | 実務にも直結しやすく頻出 |
| 統計 | 平均値、分散、標準偏差、変動係数 | 計算問題で安定して出題される |
| 推定と検定 | 標本平均、標準誤差、信頼区間の公式 | 難問でもよく出る |
| 工程能力指数 | Cp, Cpk | 実務寄り・公式で得点できる |
✅ ステップ2:過去問から出題パターンを分析する
過去問から出題パターンを分析することは、とても有効かつ効率的です。
過去問題集をざっと見て、まずは感覚をつかんでおきます。
- この公式、また出てる!
- この公式は一度も見たことないな…
✅チェックポイント:
- 公式が直接問われているか?
- 数値代入や図と組み合わされて出題されているか?
✅ ステップ3:公式を“覚える”ではなく“使える”ようにする
公式を“覚える”ではなく“使える”ようにしておく必要があります。
- 公式カードや暗記シートを使って、書いて覚えるのではなく、実際に問題を解いて覚えること。
- 「公式→問題に適用→解けた!」という体験を繰り返すことで、自然に頭に入る。
✅ ステップ4:捨てた公式は「必要なら直前に見返すだけ」
捨てた公式は、必要なら直前に見返すだけに留めておきます。
なぜなら、あまり出ない公式に時間をかけても得点にならないから。
出題率が1〜2割以下の公式は、「まとめシートの末尾」や「問題集の後ろ」にまとめる程度で良いです。
捨てた公式は、直前に1回だけ流し読みでOK。
◆ステップ1~4の方法が有効な理由
ステップ1~4の方法が有効な理由は下にまとめておきます。
| 理由 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 効率がいい | 出題率が高い公式に時間を集中投下 |
| ✅ 覚える量が絞られる | 精神的負担が軽減される |
| ✅ 試験本番で“見たことある”問題が増える | 繰り返し触れた公式が多く出てくるため、安心して解ける |
公式を使った問題を解くための学習は、“量”ではなく“質と選択”にかかっています。
QC検定2級の勉強で大切なのは、「全部やろうとしない勇気」。
“よく出るものだけ”に絞って徹底的に活用することが、最短合格への近道です。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
過去問の選択肢を暗記する学習法
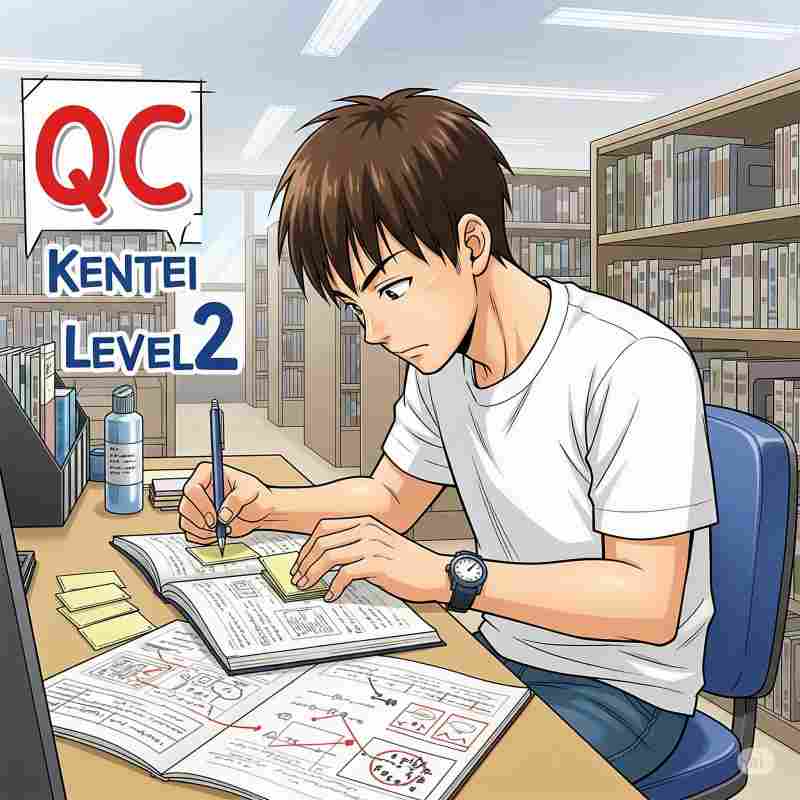
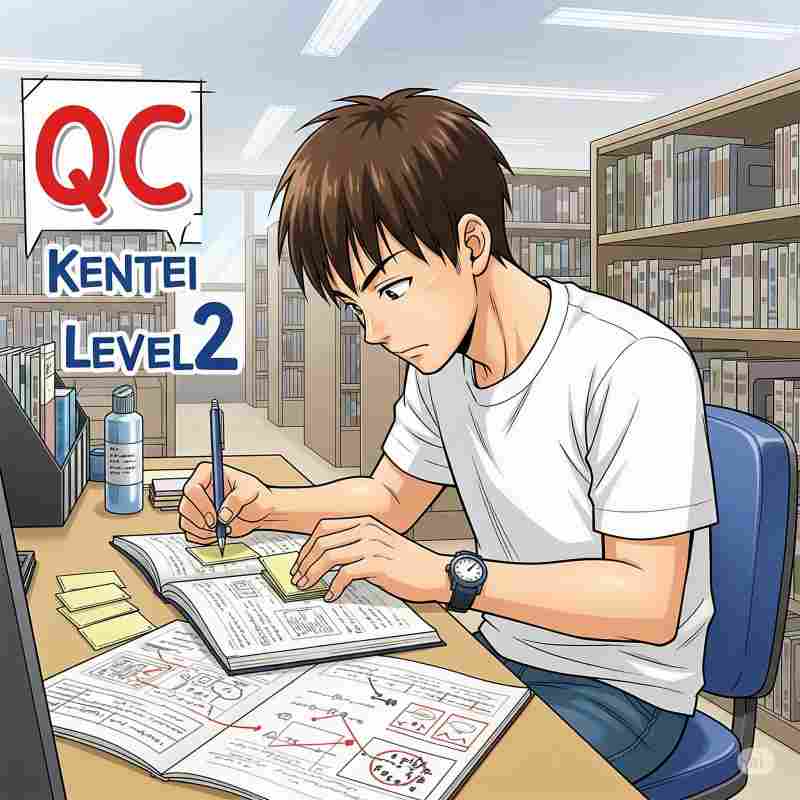
QC検定2級において、「過去問の選択肢を暗記する」学習法をおすすめします。
選択肢を見ただけで、答えが出る状態を作り出せるようになるから。
「あのフレーズ=正しい(または誤り)」という知識を蓄積することがポイントになります。
特に暗記や文章問題に強くない人は、点が取れる“裏技的テクニック”で有効です。
「なぜ選択肢暗記が効くのか?」について、理由を述べていきます。
✅ 理由1:出題傾向が固定されている
理由の一つ目は、出題傾向が固定されていることです。
QC検定の選択肢は、「用語の定義」「○×の判定」「分類」など、毎回似たパターンで出題されています。
たとえばこんな感じです。
問題:「抜取検査はすべての製品を対象とする検査である。」
解答:「✖」一部のサンプルを抜き取って検査し、その結果に基づいてロット全体の品質を判断する方法
このような「✖」の選択肢は、何度も形を変えて出題されます。
✅ 理由2:文言のクセがある
出題文には、文言のクセが出ています。
問題文や選択肢には、日科技連独特の書き方や定型表現があります。
たとえばこんな感じです。
| 出題文 | 意図するところ |
|---|---|
| 統計的に意味のある差 | t検定やF検定の話 |
| 工程能力指数が1を下回る | 不適合の可能性大 |
一度覚えると、次に見たときにピンとくるので、暗記した方が得点源になりやすいです。
「選択肢を覚える=正答のパターン記憶」
「選択肢を覚える=正答のパターン記憶」になります。
なぜなら、QC検定は出題傾向が固定されている傾向にあるからです。
選択肢のクセと答えのパターンに慣れることで、短時間で得点が稼げるようになります。
「選択肢の暗記」はズルではなく、頻出フレーズを知っておく“実戦力”の一部です。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
選択肢から逆算する学習法
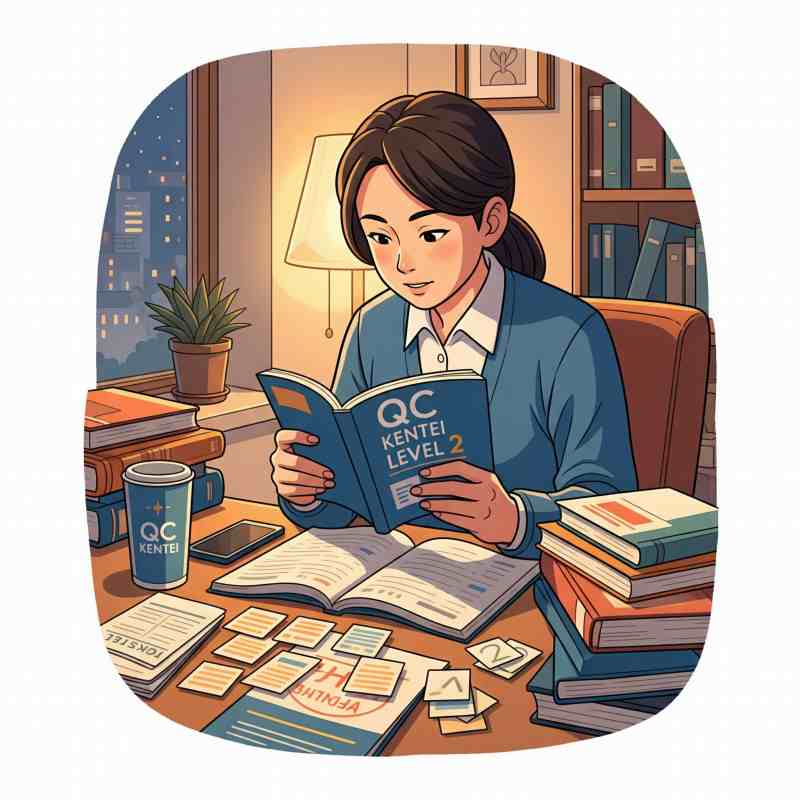
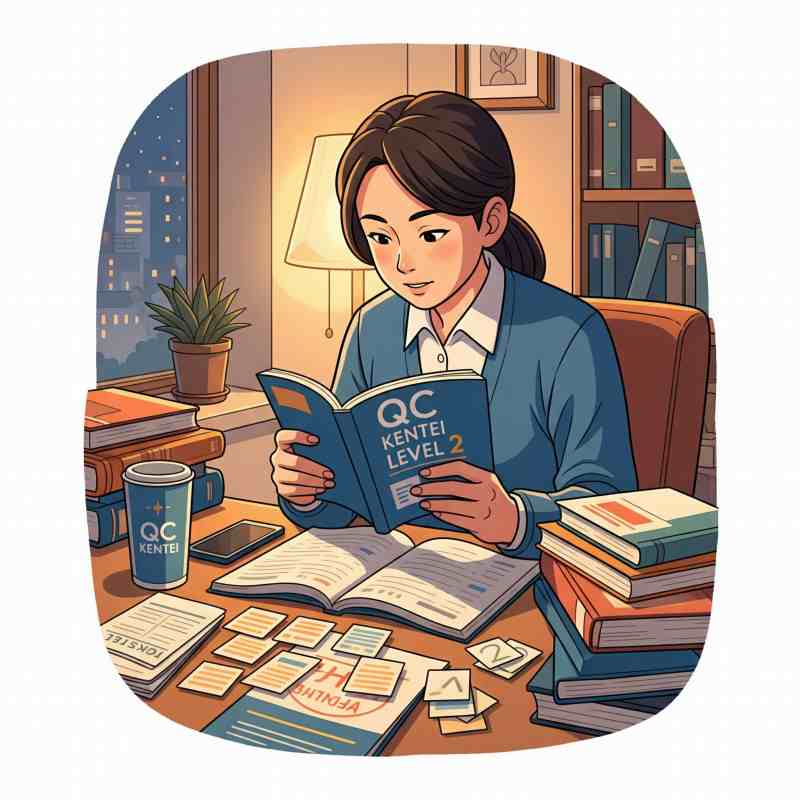
「選択肢から逆算」する学習法の具体的な方法を解説していきます。
過去問の選択肢から逆算する学習法で得点を稼ぎましょう。
ステップ①:過去問を選択肢ごとに「分解」して覚える
過去問を選択肢ごとに「分解」して覚えることは、かなり有効な方法になります。
🔶選択肢ごとに「分解」して覚える
- 過去問を使い、選択肢一つひとつに「〇・×」を書き込む
- なぜ「○」なのか、「×」なのかをすぐ横に一言だけメモ
たとえばこんな感じで、メモを一言だけ書き込んでいきます。
| 選択肢 | 正誤 ○× | メモ |
|---|---|---|
| 抜取検査では全数を調べる | × | 全数ではなく一部 |
| 管理図では異常原因を見つける | ○ | 管理図の目的 |
| 特性要因図では工程の変動を把握する | ○ | 見える化の手法 |
こうしておくと、繰り返し出る文言が浮かび上がってきます。
ステップ②:よく出るフレーズを「暗記カード化」
よく出る問題文のフレーズを「暗記カード化」すれば、スキマ時間などに覚えることができます。
「この選択肢、また見たことある…」を増やすと、かなり得点アップが見込めます。
出題頻度が高いフレーズだけを抜き出して、クイズ形式にして覚えるのも有効。
「〇」「×」パターン別の暗記カード例(クイズ形式)
形式:表面→裏面で使えるように記述
表面①:「管理図は工程が安定しているかどうかを判断する手法である」
裏面①:〇(正解)/管理図の基本的目的は「安定状態の把握」
表面②:「抜取検査では、すべての製品を対象に検査する」
裏面②:×(誤り)/全数検査の説明であり、抜取は一部のみを検査
表面③:「パレート図は、重要な問題を把握して優先順位をつけるために用いられる」
裏面③:〇(正解)/「少数の重要な要因」に焦点を当てる分析手法
表面④:「F検定は、2つの母集団の平均値の差を検定するために用いられる」
裏面④:×(誤り)/F検定は分散の比較、平均値はt検定で行う
表面⑤:「ヒストグラムは、データのばらつきや分布の形を視覚的に示すために使われる」
裏面⑤:〇(正解)/QC七つ道具の基本。階級・度数・範囲に注目
表面⑥:「Cpkは工程の中心からのズレを考慮しない能力指数である」
裏面⑥:×(誤り)/Cpkはズレを考慮する。Cpがズレを考慮しない
表面⑦:「特性要因図では、問題の原因を構造的に整理しやすい」
裏面⑦:〇(正解)/特性要因図=魚の骨、4Mなどで分類される
表面⑧:「層別とは、ばらつきをできるだけなくすための工程改善手法である」
裏面⑧:×(誤り)/層別は「分類する」手法であり、改善策ではない
ステップ③:「逆算」テクニックを磨く
選択肢を読んでから「この言い回しは〇のパターンだな」「この語尾のせいで×だ」と判断できるようにする。
選択肢からの「逆算」テクニックを磨くことで、回答スピードと正答率が上がります。
たとえばこんな感じです。
| 文言のパターン | 〇×傾向 | 解説 |
|---|---|---|
| 「常に~でなければならない」 | ×が多い | 絶対表現は誤りになりやすい |
| 「~の傾向がある」「~ことが多い」 | 〇が多い | あいまい表現は正しい場合が多い |
| 「抜取検査は全数検査の一種である」 | × | 用語の取り違え |
選択肢から逆算する学習法のメリット
選択肢から逆算する学習法のメリットを挙げておきます。
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 暗記力が活きる | 用語や意味を一から考えるより「見たことある」で選べる |
| 理解不足でも点が取れる | 内容を完全に理解していなくても選べることがある |
| 時間短縮になる | 選択肢から推測するだけで早く解ける |
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
間違いノートを作らない
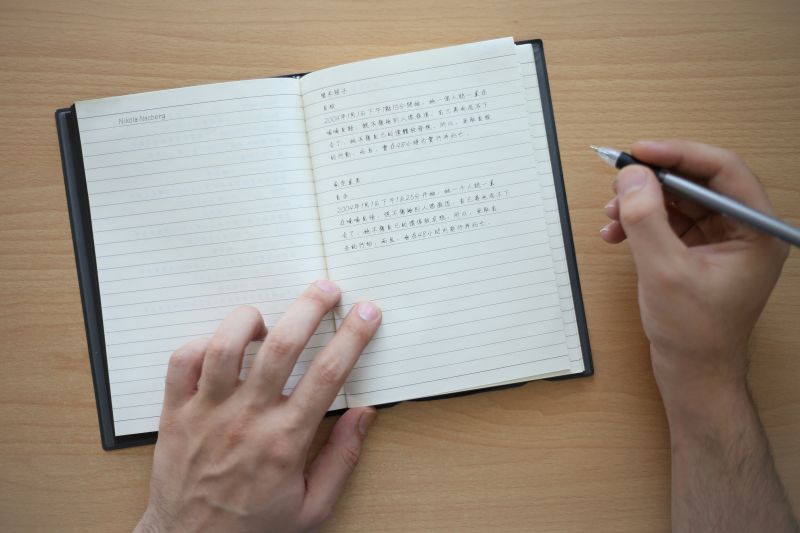
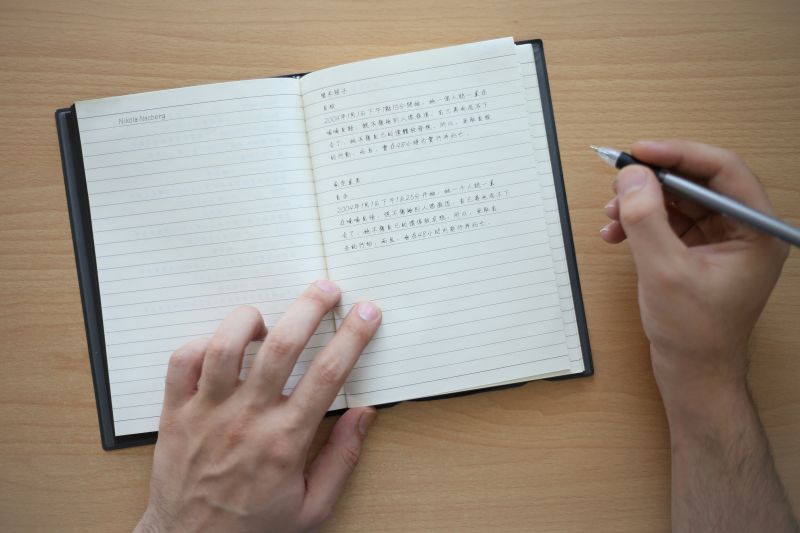
間違いノートを作らないという学習法の考え方をお伝えします。
QC検定2級で間違いノートを作らないというのは、ちょっと意外かもしれません。
効率重視の裏技的な学習法のひとつです。
「間違いノートに時間をかけるくらいなら、実践と復習に集中した方が合格に近づく」という考え方です。
- 時間対効果が悪い
- 「理解」より「整理」に時間を使ってしまう
- すぐに見返さないノートは宝の持ち腐れ
✖時間対効果が悪い
QC検定2級の範囲は広く、かつ計算問題や統計知識も多く含まれます。
間違いノートを1問ずつ丁寧にまとめる作業は膨大な時間と労力がかかります。
その時間を使うなら、再度問題を解く方が記憶にも定着しやすいのです。
✖「理解」より「整理」に時間を使ってしまう
ノートを作ると「勉強した気分」になります。
手を動かして整理しているだけで、思考の定着は浅くなりがち。
ノート作成よりも「なぜ間違えたのか」「どうすれば次は正解できるのか」の方が効果的です。
✖すぐに見返さないノートは宝の持ち腐れ
すぐに見返さないノートは、宝の持ち腐れになります。
なぜなら、QC検定2級の勉強では、演習量が合格のカギと言えるから。
ノートを後から見返す時間よりも、同じ問題を間隔を空けてもう一度解く方が学習効果が高いです。
その結果、短期記憶が長期記憶に変わります。



じゃあ代わりにどうすればいいの?
- 間違えた問題には「印」をつける
- 間違いの「原因」だけをメモ帳アプリなどに短くメモ
- 過去問で“実戦形式”に慣れることを優先
✅ 1. 間違えた問題には「印」をつける
間違えた問題には、「印」をつけることをおすすめします。
2周目、3周目で間違えた問題だけを繰り返し解くことで、効率よく弱点を潰せます。
過去問や問題集に直接、チェックマークや付箋などで「間違えた」印を残しましょう。
✅ 2. 間違いの「原因」だけをメモ帳アプリなどに短くメモ
間違いの「原因」だけをメモ帳アプリなどに短くメモしておくだけに留めましょう。
なぜなら、必要最低限だけにすることで見返しやすくなります。
たとえば「母集団分布と標本分布を混同した」など、1行で済ませます。
ポイントは「書きすぎない」こと。
✅ 3. 過去問で“実戦形式”に慣れることを優先
過去問で“実戦形式”に慣れることを優先しましょう。
なぜならQC検定2級は、過去問からの出題傾向が強いから。
間違いノートを作るより、時間を測って実戦形式で解き、解説で確認するという流れを何度も繰り返す方が本番に強くなります。
QC検定2級は暗記よりも理解力と運用力が問われる試験なので、問題を多く解くことを優先すべきです。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
捨て問を決めて時間配分する
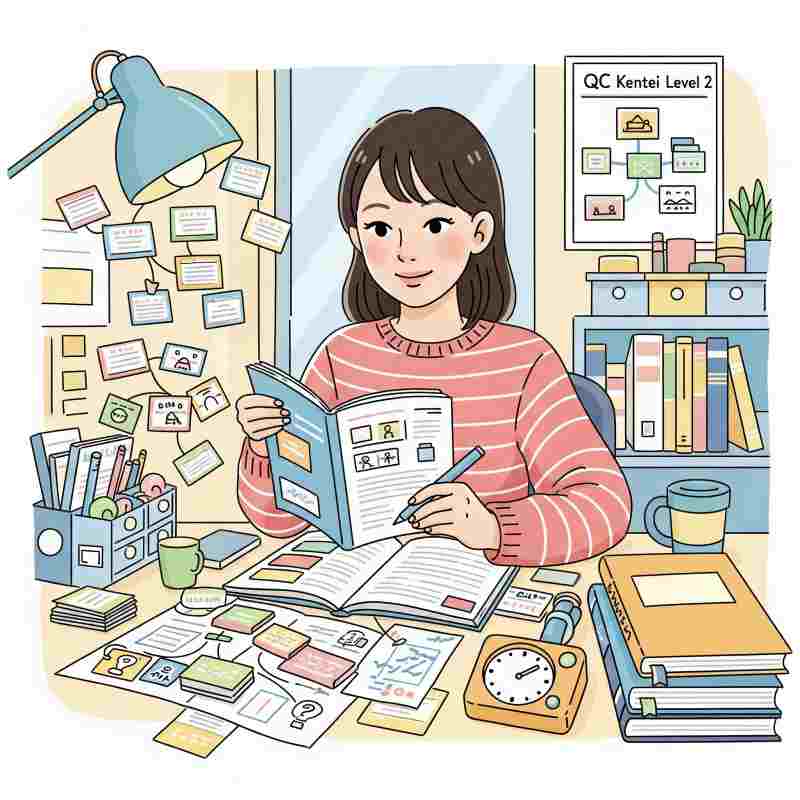
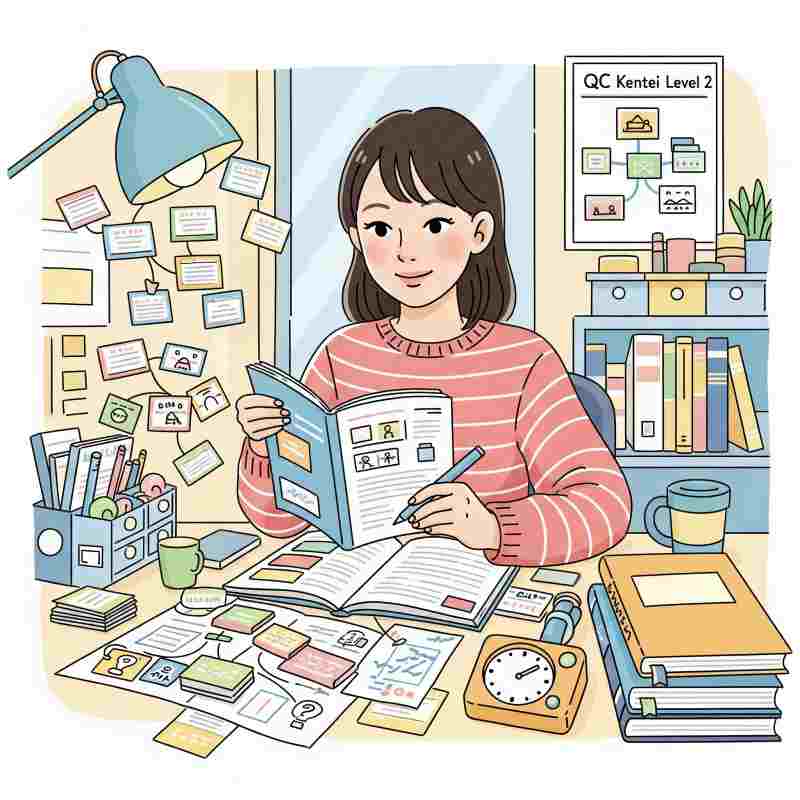
QC検定2級において、捨て問を決めて時間配分することは、是非取り入れて欲しい考え方です。
なぜなら、難易度が高く、範囲も広いため、すべての問題に全力で挑むのは非効率だから。
「あえて取らない(または後回しにする)問題=捨て問」を事前に決めておくことで、合格に必要な70点(約28問)を最短で確保できます。
全問正解を目指さず、“合格に必要な点だけを効率的に取る”ための、非常に有効な裏技的戦略です。
🔶この戦略の目的
- 試験中に焦らない
- 合格点に必要な問題だけに集中
- 時間切れで終わらないようにする
◆QC検定2級の概要(ざっくり構成)
| 分野 | 出題傾向 |
|---|---|
| 品質管理の基本 | 用語・定義・基礎知識が中心(狙い目) |
| 統計的手法 | 計算問題・応用問題あり(得意なら狙い目) |
| 新QC七つ道具 | 少しマイナーで出題数は少なめ |
| 抜取検査 | 出題されるが難問も含む |
| 管理図 | 頻出で得点源にもなる |
| 推定・検定 | 難問多し(捨て問候補) |
具体的な「捨て問戦略」ステップ
✅ ステップ1:過去問を使って「自分の得意・不得意分野」を知る
過去問を使って「あなたの得意・不得意分野」を知っておくことが大事です。
問題ごとに3段階でチェック。
- 解けた
- 時間がかかった
- 手が出なかった
たとえば、検定・分散分析・計算問題などが苦手なら「捨て問」に回すのも戦略。
✅ ステップ2:「絶対取る」問題と「最初から捨てる」問題を分ける
「絶対取る」問題と、「最初から捨てる」問題を分けて、優先度をチェック。
| 優先度 | 内容 | 時間配分の目安 |
|---|---|---|
| ★★★ 必ず取る(◎) | 用語・定義、基本的な公式、グラフ読み取り | 40分以内で解答する |
| ★★ 取れたらラッキー(〇) | 中レベルの計算・工程能力指数など | 時間があれば挑戦(20分以内) |
| ★ 捨てる・後回し(×) | t検定・F検定・母集団分布などの応用問題 | 最後の10分で余裕があれば |
✅ ステップ3:試験本番での時間配分戦略(例:90分の試験)
試験本番での時間配分を戦略的に決めておくと、どんな問題が出ても慌てないですみます。(例:90分の試験)
| 時間帯 | 行動 |
|---|---|
| 0~10分 | 全体をざっと見て、◎問題だけ先にマーク(捨て問候補もチェック) |
| 10~50分 | ◎問題をすべて解く(時間配分は1問2分目安) |
| 50~70分 | 〇問題にチャレンジ。計算問題も含めて部分点狙い |
| 70~90分 | 捨て問×に挑戦。余裕があれば計算・検定などを再チャレンジ。未回答を埋める |
◆「捨て問」の決め方のコツ
QC検定2級の「捨て問」の決め方について、コツを挙げておきます。
| 問題のタイプ | 捨てるべきサイン |
|---|---|
| 計算系 | 「公式が複雑すぎる」「途中式が思い出せない」 |
| 推定・検定 | 「z検定?t検定?混乱する」「分母が思い出せない」 |
| 応用記述 | 「そもそも何を問われているかピンとこない」 |
| 新QC七つ道具 | 「具体的な事例と結びつかない」 |
◆実際の点数戦略(例)
QC検定2級は全40問中28問(=70点)正解すれば合格。
| 問題タイプ | 問題数 | 正答目標 |
|---|---|---|
| ◎(確実に取る) | 25問程度 | 22問正解(88%) |
| 〇(取れたらOK) | 10問程度 | 4問正解(40%) |
| ×(捨て問) | 5問程度 | 1問でも正解できればラッキー |
点数の合計点が「22+4+1=27点(67.5点)でも合格圏に入る可能性があります。
確実に28問を目指せば◎。
ただし、手法編と実践編の各分野50%以上の点数が必要なので、問題の配分を確認しておきましょう。
◆捨てる勇気が受かる力になる
範囲が広く、難易度が高いQC検定2級において、捨てる勇気が受かる力になります。
QC検定2級で合格したいなら、「全部解けなくても合格できる」という現実を活かすことがカギです。
「捨て問を見極めて、得点ゾーンに集中する」メリハリが、時間もメンタルも守ってくれます。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
まとめ QC検定2級の【裏ワザ】的な最短で合格するテクニック5選
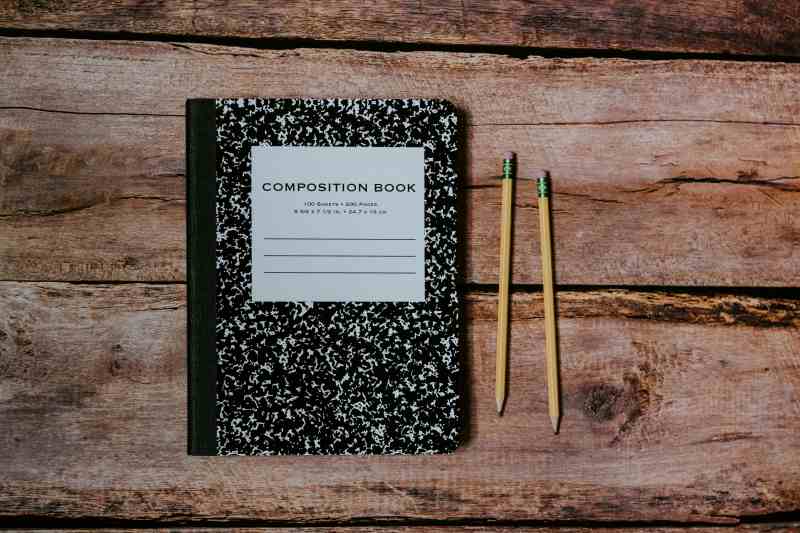
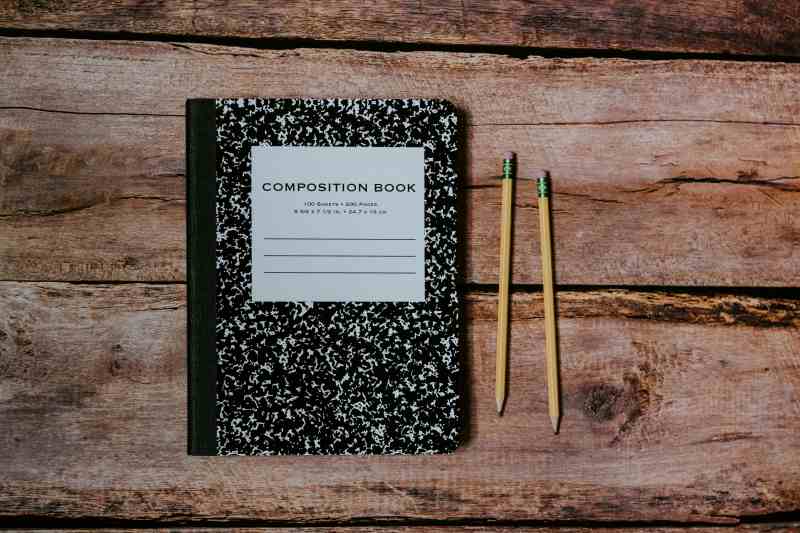
この記事では、QC検定2級の【裏ワザ】的な最短で合格するテクニックを紹介してきました。
- よく出る公式だけ覚える
- 過去問の選択肢を暗記する学習法
- 選択肢から逆算する学習法
- 間違いノートを作らない
- 捨て問を決めて時間配分する
品質管理の知識を問う実務的な検定として、多くの社会人にとってキャリアアップの登竜門とされています。
しかし「範囲が広い」「計算問題が難しい」と、壁にぶつかる人も少なくありません。
「とにかく受かりたい」「遠回りはしたくない」と、お考えのあなたのための記事です。
初受験の方はもちろん、一度つまずいた経験がある方にも役立つ内容になっています。
QC検定2級の学習方法には、独学と通信講座があります
●独学学習なら、テキストや過去問の選び方が最重要です
●通信講座をお考えの方には、この3社がおすすめ
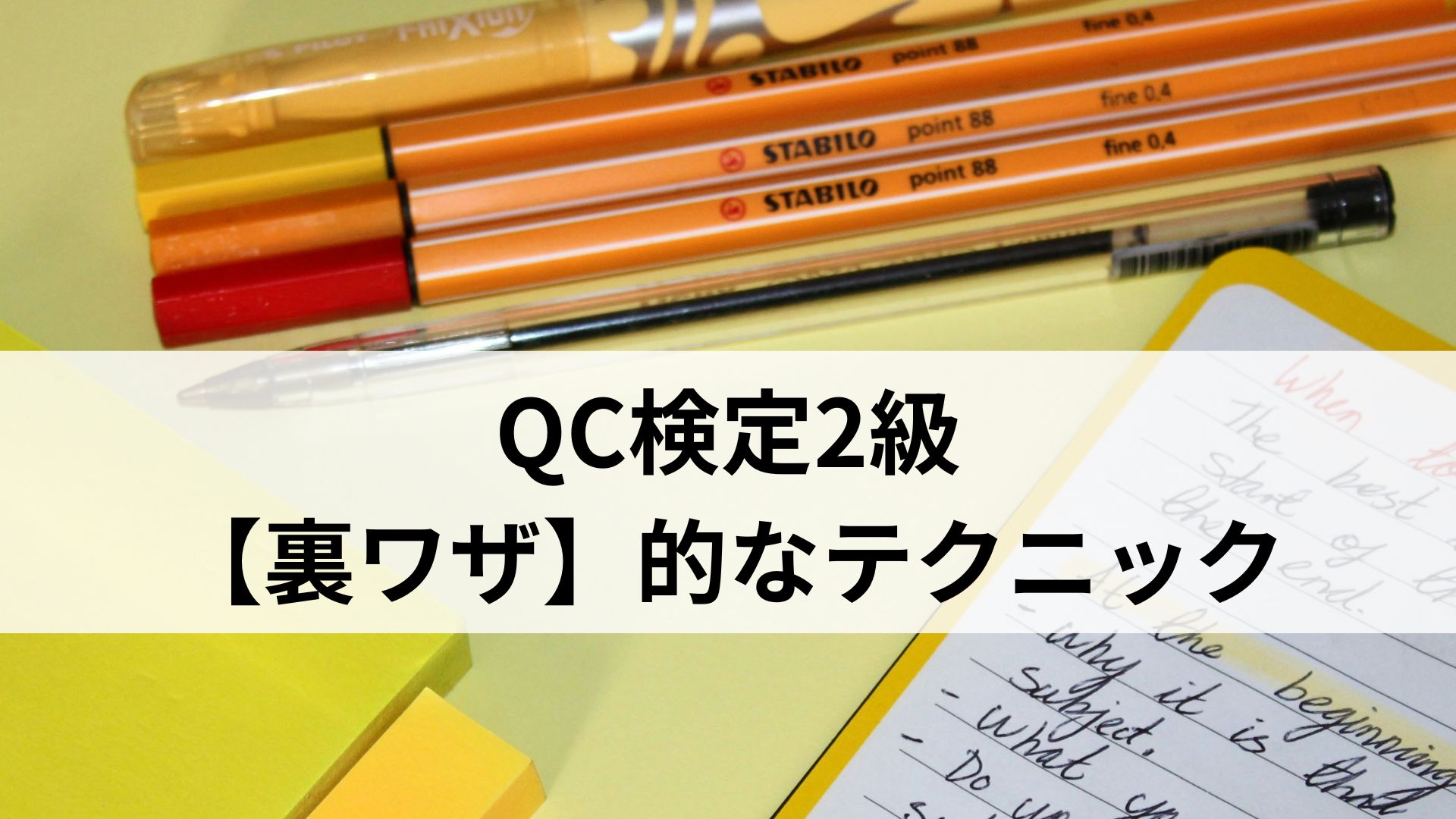
コメント